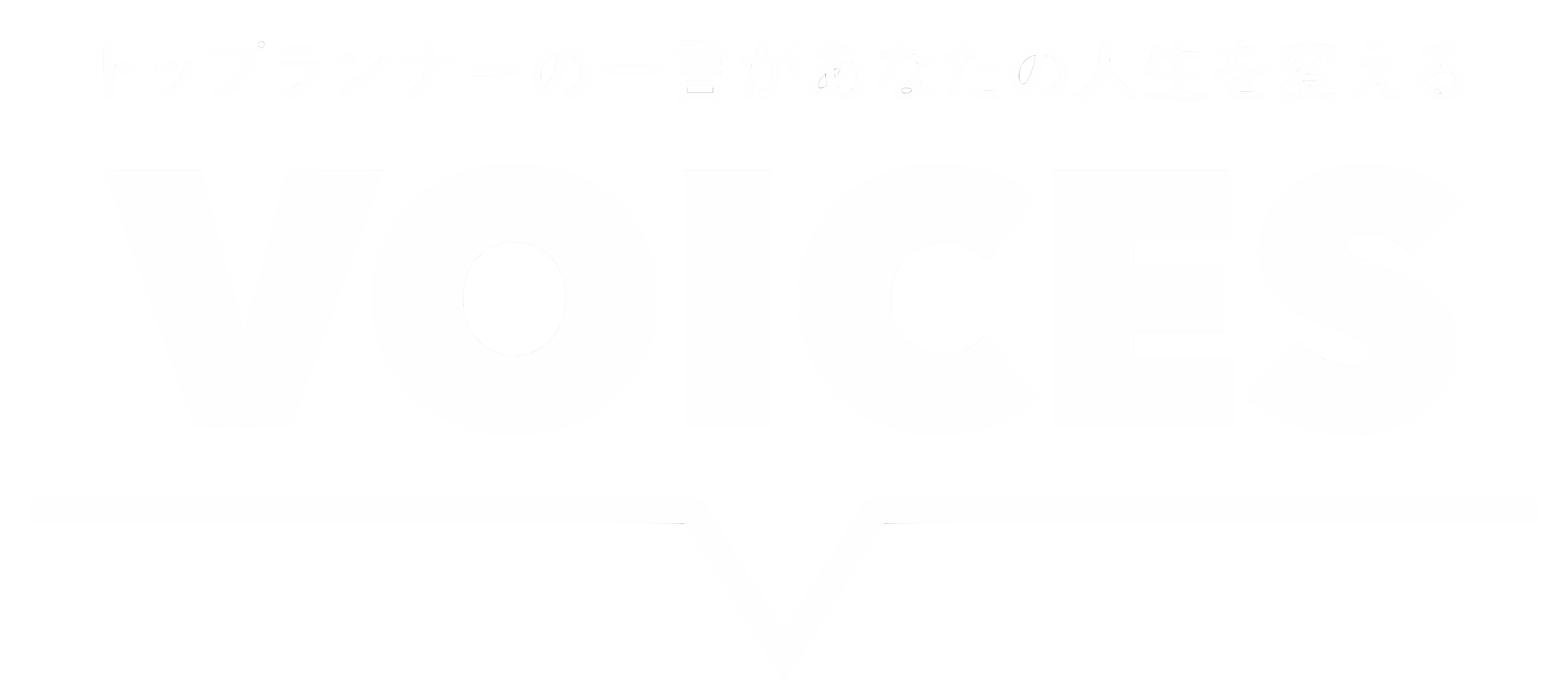最近は脳の動脈瘤の手術でもカテーテルによる血管内治療が増えています。開頭して病変を直接観察しながら行う手術とは違い、手首や太ももの動脈にカテーテルを挿入し、病変部に到達させて治療します。カテーテルのほうが到達しやすい部分には確かに向いていますが、この方法では治療できない動脈瘤もあるんですね。そういう患者さんが私たちのところに来るわけです。だから難しい症例が多くなるんですよ。
カテーテルをやっている人たちが、これは自分の領域ではないと言っても患者さんはどうにかしてあげなくちゃいけない。今後、カテーテルによる血管内治療に頼りすぎると、手術の経験値が低い医者ばかりになって、治療してもらえない患者さんが出てくるのではないかと心配しています。そんなわけで、血管内治療ができないとか、動脈瘤がすごく大きいとか、複雑なクリップをつけないといけないなど、他の病院でどうにもできないと言われた患者さんが、恐怖心を抱えたまま私たちのところに来ることも多いんですね。診察して、この動脈瘤は破けないから大丈夫と言うと、ほっとした顔をされます。正確な知識を伝えて、他の専門家に任せたほうがいい場合は紹介します。東京と名古屋の病院に知り合いが多いので、それぞれの科のどの先生がいいのかを調べることもできます。患者さんはどうしたらいいかわからないので、できることは私が代わりにやるようにしています。自分のところで手術をする時は、安全なのか、難しいのか、どういうことをする手術なのかをきちんと説明して、その通りの手術をします。患者さんの身になって、何をしてあげるのがいちばんいいかを考え、自分にできる最善のことをするんです。
今後、AIやロボットの導入で医療は変わっていきます。内科の診断には、膨大なデータを参照できるが使われるでしょう。お腹や肺の手術にはロボットが活躍すると思います。ロボットは手ぶれ補正が効きますから、縫合もスムーズです。脳の手術ではミリ前後の血管をつなぐことが多いので、そこをロボットが正確にやってくれると助かるのですが、今のところ、脳にはロボットが入るようなスペースはありません。我々は脳に手を入れた時、道具を通して手に伝わってくる感触を、危ないと思って引くことがあるんです。そういうことがロボットにできるのかどうかは、まだわかりません。医療にどんな未来が訪れても、天命に従い、患者さんのために尽くす。これしかないと私は思っています。